機能性表示、「回復」「緩和」も可能に 消費者庁・塩澤氏が説明(2015.2.23)
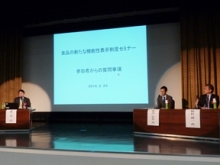
消費者庁食品表示企画課の塩澤信良調査官は23日、大阪商工会議所主催の「食品の新たな機能性表示制度セミナー」に登壇し、機能性表示食品制度における可能な機能性表示の範囲について、「回復」「緩和」の表現は「健康の維持・増進の範疇で使うのであれば、直ちに医薬品の表示(旧薬事法)に抵触するものではないと定義した」と述べた。
1月14日に開催された規制改革会議健康・医療ワーキンググループで同庁が提出した新制度の「届出に関するガイドライン(案)の概要」では、いずれの表現も「医学的な表現に当たるため使用できない」とされていた。その後、厚生労働省などとの間で調整を行ったという。
回復、緩和の表現について塩澤調査官は、「適切に使うのであればダメではない」と明言。ただ、「文言のみならず、パッケージ全体で、病気の回復や緩和を示唆するような表現は今回の制度の範疇外」だと釘を刺し、適切な使用を求めた。一方、「診断」「予防」「治療」「処置」などの表現は、医学的な表現に当たるとしている。
また塩澤調査官は、有効性評価方法の一つとなるシステマティックレビュー結果の報告方法についても説明し、「(消費者庁に届け出る)報告書については、PRISMA声明(2009)に準拠した形式で記載されていることを原則とする」とした。
同セミナーには業界関係者約700名が聴講に訪れ、会場は満席状態。主催関係者の事前予測に反し、届出ガイドラインが公表されないままでの開催となった。その公表時期について塩澤調査官は「近々の予定」だとコメント。同庁は来月2日から、東京を皮切りに全国7都市で新たな機能性表示制度に関する説明会を行う予定にしており、来月2日までに公開される可能性が極めて高い。
【写真はセミナーの様子(23日、大阪・中央区)】










